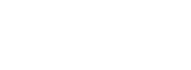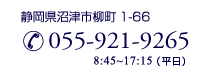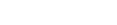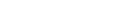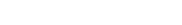派遣法の改正案は、これまでの労働者派遣をとりまく課題への対応をして策定されました。
どういった内容が改正されたのかは、下記でご説明させて頂きます。
1.期間制限のルール変更
①派遣先事業所ごとの期間制限
同じ派遣先の事業所に、派遣できる期間は最長3年。
ただし、派遣先の労働者の過半数代表の意見聴取を期限1ヶ月前までに行うことにより更新可能(1回の延長期間は最長3年)。
②派遣労働者ごとの期間制限
同じ派遣労働者を、派遣先の事業所における同一の組織単位(「課」を想定、以下「課」)に対し、派遣できる期間は最長3年。
つまり、同じ人は3年を超えて同じ「課」へ派遣できない。
ただし、派遣元で無期雇用されている派遣労働者、60歳以上の派遣労働者は対象外。
2.派遣先への義務
(1)労働契約申し込み見なし制度(派遣先への義務、H27年10月1日より適用~)
派遣先が次の違法派遣を受け入れた場合、その時点で派遣先が派遣元と同じ労働条件で派遣労働者に労働契約の申込みをしたものとみなされます。ただし、違法派遣について、派遣先が善意無過失である場合を除きます。
①労働者派遣の禁止業務に従事させた場合
②無許可の事業主から労働者派遣を受け入れた場合
③派遣可能期間を超えて労働者派遣を受け入れた場合
④いわゆる偽装請負の場合
(2)派遣労働者と派遣先社員の均等待遇(派遣先への義務)
派遣先企業は、派遣労働者と派遣先で同種の業務に従事する労働者の待遇の均衡を図るため配慮義務が課され、次の具体的な行動を行う必要があります。
①派遣元事業主に対し、派遣先の労働者に関する賃金水準の情報提供等を行うこと
②派遣先の労働者に業務に密接に関連した教育訓練を実施する場合に派遣労働者にも実施すること
③派遣労働者に対し、派遣先の労働者が利用する一定の福利厚生施設の利用の機会を与えること
(3)派遣労働者へのキャリアアップ支援
①3.(4)のキャリアアップ支援に役立つような派遣労働者の職務遂行状況や、職務遂行能力の向上度合などの情報を派遣元から求められたときは提供するように努めなければなりません(努力義務)。
②派遣労働者を受け入れていた「課」に派遣終了後に同じ業務の労働者を雇い入れようとする際に、その「課」で同じ業務に1年以上従事した派遣労働者がいる場合には、その派遣労働者を雇い入れるよう努めなければなりません(努力義務)。
③派遣先の事業所で正社員募集を行う際に、1年以上従事した派遣労働者がいる場合には、その募集情報を周知しなければなりません(義務)。
④正社員に限らず、派遣先の事業所で労働者の募集を行う際に、その「課」で3年間従事した派遣労働者がいる場合には、その募集情報を周知しなければなりません(義務)。
3.派遣元への義務等
(1)特定労働者派遣が廃止、許可制に(新たな許可基準の詳細は後日、3年の経過措置)
(2)就業条件の明示(派遣元への義務)
派遣元は、派遣労働者に対して就業条件などを明示する際に、1.の期間制限違反が(1)労働契約申込みみなし制度の対象となる旨も明示しなければなりません。
(3)派遣元事業主への雇用安定措置
同じ組織に3年間継続して派遣される見込みがある場合、派遣終了後に、次の雇用安定措置を講じる義務があります。
①派遣先への直接雇用の依頼
②新たな派遣先の提供(合理的なものに限る)
③派遣元での(派遣労働者以外としての)無期雇用
④その他安定した雇用の継続を図るための措置
(4)キャリアアップ措置の実施義務(派遣元)
①段階的かつ体系的な教育訓練
②希望者にキャリア・コンサルティング
特に、無期雇用派遣労働者に対しては、長期的なキャリア形成を視野に入れた教育訓練を実施することが派遣元に義務付けられます。
(5)均等待遇の推進について説明義務(派遣元の義務)
派遣労働者が求めた場合、派遣元から、賃金の決定、教育訓練の実施、福利厚生の実施について、派遣労働者と派遣先で同種の業務に従事する労働者の待遇の均衡を図るために考慮した内容を説明する義務があります。
(6)派遣元管理台帳への追加記載(派遣元の義務)
①無期雇用派遣労働者であるか有期雇用派遣労働者であるかの別
②雇用安定措置として講じた内容
③段階的かつ体系的な教育訓練を行った日時および内容